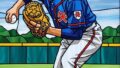Baseball Elegy with Sons
~いま振り返る、親おやドキュメント~
地元の小学生野球チームから中学生のクラブチーム。
子ども3人トータル11年、野球少年の親を経験したおやじの奮闘記です。
「あるある」と笑ってください。
「わかるわかる」と泣いてください。
こいつが少年野球親のドキュメントです。
グローブ購入事件
小学4年生の長男が、地元の野球チームに入りたいと言ってきた。
おそらく友達に誘われたのだろう。ちゃんと学校や同級生となじんで生活できてるんだなと、それがうれしかった。
兄に感化されたのか、小学2年生の二男も入りたいと言い出した。
こうして我が家に突然、少年野球がやってきた。
早速、妻が、野球チームの練習に二人を連れて行った。
いわゆる体験入部というやつだ。
チーム首脳陣や部員の父母など、関係者のみなさんが雰囲気の良さをアピールしてくる。
(体験入部だからだろうな)
わかっているのだが、居心地がいいので、こっちも笑顔を安売りしてしまい、
(入部しますよね〜)
という空気を跳ね返せない。
なんかマルチ商法のにおい。恐るべし、体験入部!
練習は土日と祝日だけ。
そういう意味では親の負担も想像がつくし、子どもも最初から入部するつもり。
ということで、後日、入部届を提出。
「まずはグローブを用意してください。バットは後からでもいいです。」
「あのーグローブって、どんなものがいいとかありますか?」
恐る恐る妻がたずねる。
「何でもいいですよ」
(そうだろうな)
その話を妻から聞いて、そう思った。
最初から有名なメーカーの値段が高いグローブを持たせても、どうせ下手くそだろうし、手入れもできないだろう。安いつぶしのきくグローブがいいと、私の中で合点がいった。
ということで、トイ◯◯スという大型のおもちゃ屋に行った。販売されているグローブは割と種類豊富で、見た目スポーツメーカーのものとそんなに遜色ないものもあり、「安いしちょうどいい」と、満足感を持って買って帰った。
そして、正式入部後、初練習に行くと、いきなりコーチらしき人に言われた。
「そのグローブはダメだよ」
「えっ」
「だって、それおもちゃじゃん」
半笑いで言われた。

何でもいいとしか言わないのが不親切だとか、こちらの確認不足だとか、原因を追及するのが、この場合不毛だということは理解している。
私の感覚では、半笑いからの「おもちゃじゃん」は、もはや暴力である。
お金出して買ってるんですよ。それを抱えた子どもも目の前にいるんですよ。
自分の親が小馬鹿にされた感じ、子どもも感じてるじゃないですか。
言い方ってあるじゃないですか。
その日、うちの子どもたちは、部員にグローブをからかわれながら、入部初日を終えた。
すぐに遅くまで開いてるスポーツショップを探し、ミズノのグローブを買い直した。
波乱の幕開けである。
おもちゃのグローブは、しばらく私が使った。
ああ、監督、コーチよ
チームの監督は、60代の男性。
地元の方で、かなり前から監督をされているとのこと。時間に自由がきく仕事をされている。
ゆったりめにしゃべる姿は、年齢より老けて見えるが、たまにノックを打つ。
「今日からよろしくお願いします」
入部初日、二人の子どもと私と妻で挨拶したが、笑顔は見せていただけなかった。そもそも笑顔の少ない、ぼやきの多い方のようだ。
気さくに話せないが、気難しいとまではいかない、といった感じか。
おそらく監督と同世代ぐらいと思われるコーチがいる。監督ほど老け込んでいない。
練習中もやたらと携帯電話で話している。
声が大きく、高校野球などの話をしているのが聞こえてくる。アマチュア野球を手広く把握しているのだろうか。
ここではこのコーチを『ヘッドコーチ』と呼ぶことにする。
公式試合があるのは、6年生を中心としたレギュラーチームだが、4年生以下の低学年チームも、少ないが公式の大会が開催される。
レギュラーチームは、監督、ヘッドコーチが中心。低学年チームは4年生のお父さん達が指揮をとる。
とある日、レギュラーチームの練習試合が行われた。低学年(4年生以下)も応援に参加した。
私としては初のチームの試合観戦。なんだかワクワクした。
監督と、6年生のお父さん達(コーチ、マネージャー、スコアラー)が、選手とともにベンチに座る。ベンチといっても、小学校のグラウンドなので、長椅子が並べられただけだが。
(ん?)
ここで違和感。
ヘッドコーチは?
ヘッドコーチがベンチにいない。
ベンチの5mぐらい後方、離れた場所に椅子を置いて、ややふんぞり気味に座っている。ユニフォームも着ていない。
なぜベンチから離れているのか。
試合が始まった。
合間合間で、ベンチ後方の離れたところから、ヘッドコーチが「○○!」と選手を呼んで、守備やバッティングについて、手取り足取り、指導している。「さっきのプレイはなんだ」ってな感じ。
なぜヘッドコーチはそれをベンチでやらないのか。
答えは簡単。
監督とヘッドコーチの仲が悪いのである。
少年野球チームの指導をしている2人の高齢者が、なんと不仲!
(なんだよ、そりゃ)
そういえば、普段から話してるの見たことない。
野球指導者の地位を失いたくないから、仲が悪いまま、チームにしがみついているわけだ。
どっちがどうだか知りませんが、みっともないなぁ(ため息)
ベンチの後方でヘッドコーチが指導しているのを当然監督もわかっており、その指導を受けた選手に、やけに監督がつっかかっているように見える。
ヘッドコーチのいうことを聞いている選手に腹が立つらしい。
はぁ~(再びため息)
子ども達はどうしたらいいんでしょう。

幸いなことに、その翌年、ヘッドコーチはやめられた。
理由はわからない(いや、はっきりしてる)が、子ども達が混乱する原因は取り除かれた。
でも、私たち親から見ると、そもそも子どもの前で、いい歳をした指導者の大人が、仲違いしているみっともなさに閉口していたわけで、監督が『派遣争いの勝利者』となっただけで、不仲老人の片割れという印象はぬぐえず、不安の雲が晴れることはなかった。
自分の子どもが試合に出ている親、出ていない親
恐縮だが、私の子ども3人について。
4年生から始めた長男は、残念ながらレギュラーにはなれなかった。バッティングは光るものがあったと思うが、守備が苦手だった。代打では毎試合使ってもらい、ホームランも一本打った。
2年生から始めた次男は、やはり守備が苦戦し、レギュラーチームシーズンの前半は5年生にレギュラーをゆずった。後半はなんとか先発セカンドで試合に出ることができた。
1年生から野球を始めた三男は、5年生からサードでレギュラーとして試合に出た。6年生になってエース番号1をもらい、バッティングでも中軸を任された。投打の中心だった。
このように、当然に試合に出る子、出ない子が存在する。
レギュラーで試合に出ること、試合に出られないことの考え方や価値観の中に、私たち親は、『大人力』『親力』を試されることになる。
子どもが活躍するには、まず試合にでなければならない。
大半の親は、自分の子どもが試合に出て活躍する姿を見たいと思っている。
大事なことは、それを表に出さないことだ。
子どもがレギュラーで活躍している親は、その喜びを、間違っても発してはならない。
子どもがレギュラーになれていない親は、その悔しさを、おくびにも出してはならない。
皆、大人なので、わかっている。お互いの感情やルールも。
だが、まれにルールの認識が甘い親が実在する。
特にレギュラー組。
試合に出ていない組の親に「もうちょっとがんばれば試合に出られるよ」「なんで出られないの。上手なのに」などと、出ていない組同士なら大丈夫な発言も、レギュラー組→出ていない組の場合、ただの嫌味にしかならない。
じゃあ、あなたの子の代わりにその子がレギュラーになってもいいのですか。と、こうなる。
怖い話を一つ。
二男の代での出来事。
エースのA君が力投している試合で、サードのB君がエラーをした。
その日の夜。A君の父が、B君の父に電話したそうだ。
要件はなんと「明日、Bからうちの子に謝るように言っといて」
ぎゃー(悲鳴)
実際にあった話である。
さらにもう一つ。
C君のお父さん。少し変わり者で、あまり積極的に他の父母とコミュニケーションをとらない。みなさん適度に距離を置いている感じ。
公式戦、そのC君が打席に入った。得点のチャンス。
見事にタイムリーヒット!
1人、他の父母達から離れて座っていたC君のお父さんの、大きな声が聞こえた。
「さすが俺の息子や!」
ぎゃー(悲鳴)
炎天下のなか、みんな凍りついたそうな。
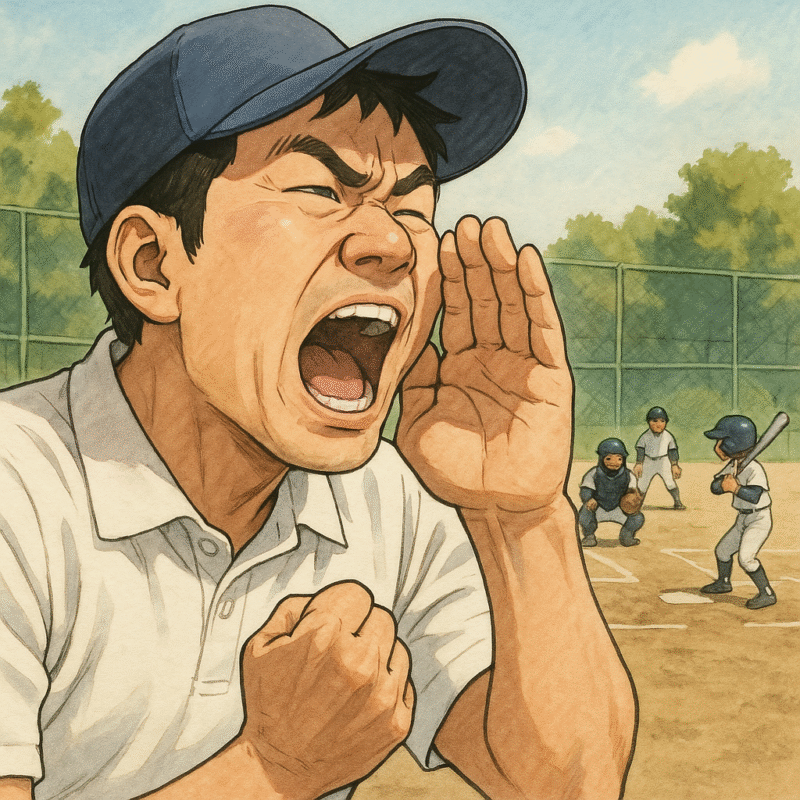
自分の子どもが他の子より野球が上手で、チームの中心で、試合で活躍するということは、親にとって、このうえない甘美なのだ。
子どもが活躍すればするほど、もっと褒めろ、もっとそれを伝えてこい、と思ってしまう。
それを、我慢しなくてはならないのだ。
それが『大人力』であり『親力』だ。
そして、それを我慢できない奴が現れる。
それも、少年野球なのだ。