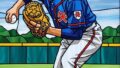Baseball Elegy with Sons
~いま振り返る、親おやドキュメント~
地元の小学生野球チームから中学生のクラブチーム。
子ども3人トータル11年、野球少年の親を経験したおやじの奮闘記です。
「あるある」と笑ってください。
「わかるわかる」と泣いてください。
こいつが少年野球親のドキュメントです。
寄生お母さん
試合の時などは、移動が生じる。遠方の場合も当然ある。
「車出し」当番の人は、選手を乗せていく。
それ以外の人は、自分の車で行くわけだが、その手段を持たない方がいらっしゃる。
例えば、車を持ってない人。
免許を持ってない人。(ペーパードライバー含む)
また、車はあるが、免許を持っている旦那が単身赴任だとか。
そういう奥さんは、『足』を探す。
不思議とこういう人は、普段からあまり好かれていない。(私の偏見です)
「ねぇ、来週乗せてもらっていい?」
「・・・あ、はい、いいですよ」
断るわけもいかず、仕方なく受け入れる。
というか、断れない人を探し出して『寄生』してくる。
申し訳ない、という感じではなく、ずかっと聞いてくる。
巧妙に、かつ力技で。(なので断りにくい)
「○時に○○に来て」
家の真ん前を指定する。またこういう人は家が遠いうえ、車が停めにくい。
「子どもの弁当作れなかったのよ。コンビニ寄ってくれない?」
「帰り、○○に寄って」
「たばこ吸っていい?」
「来月も乗せてもらっていい?」
と、こうなる。
常習的に足(車)が無いなら、そもそも交通機関を利用する気は無かったのか?
子どもが入部するときから、人の車をあてにしていたのか。
他の父母の車は、無料タクシーではない。
いろんな家庭の事情があり、やむを得ない時だってある。
助け合いも大切。
だからこそ、
交通が不便な場所の時だけにするとか。
たまにはガソリン代としていくらか出すとか。(お菓子とかでもいいし)
少しでも遠回りにならないよう、車が止めやすいところまで自分から出ていくとか。
あつかましいと思われない工夫は、いくらでもある。
それをやらないから、陰で『寄生虫』などと言われるのだ。
中学のクラブチームの時の話。
ある部員の母親が、別のお母さんに「試合の日乗せてってー」と頼んできた。
当日家に迎えに行ったら、母親、兄(大学生)、そしてなんと、その兄の彼女までもが待っていたという。きゃー!
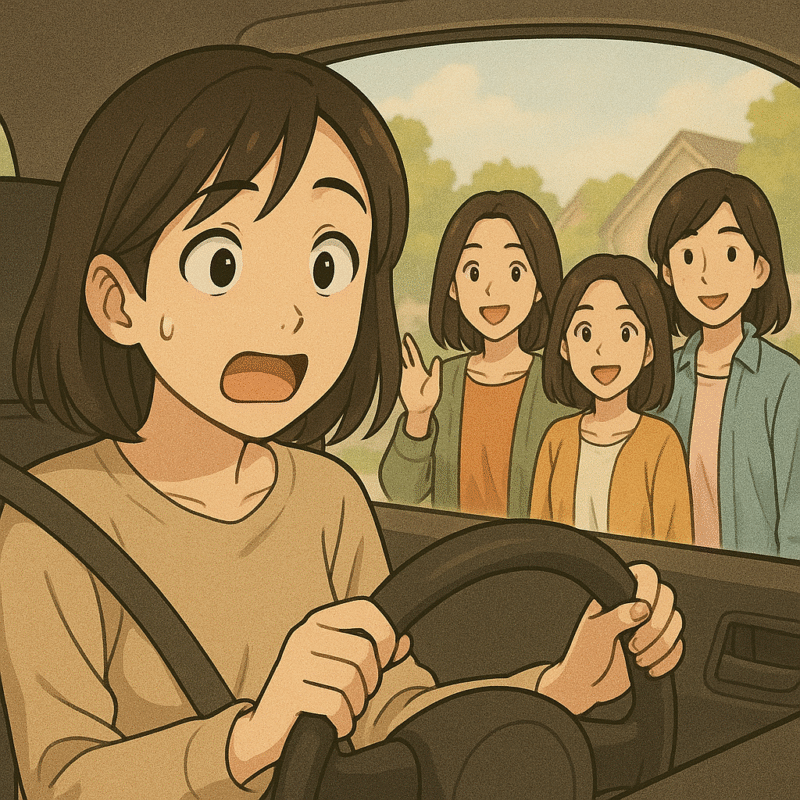
子どもが褒められた時の答えに、正解はない
これは、私が長年『父親』をやったなかで、発見したことである。
たまに、我が子を褒められる時がある。
少年野球の場面では、あいさつ代わりに、相手の子を褒めることは多い。
「○○君、守備範囲広いですね」
「○○君、スイング速いですね」
「○○君、球が伸びてますね」
「○○君、いやー上手になりましたね」
こんな感じ。
野球少年のお父さんたちなので、褒める内容も具体的である。
私はこういう場合、やや強めに否定することにしている。
「とんでもない」「いーえ、いーえ」
しっかり手を振って否定する。本気で「そう思っていないよ」とばかりに。
もちろん、うれしい。まんざらでもない。
だが、認めたら終わりだと思っている。
「社交辞令を真に受けて」と陰で笑われたくない。
しかし、否定しないお父さんも少なくない。
「確かにそうですね」
「やっと練習の成果が出てきました」
「気づいていただき、ありがとうございます」
「よく言われるんですよ」
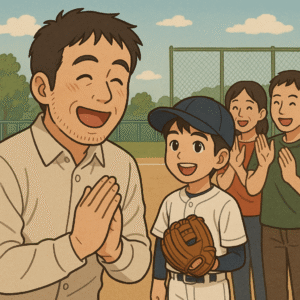
えー!っていう感じですが、そんな方々を横目に、正解は何だろうと考える。
自分の子をお褒めいただいた時・・
①否定すると
→ 自分の子を評価しない薄情な父親
②肯定すると
→ 親バカ
つまり肯定しても否定しても、よく思われない。
したがって、『子どもが褒められた時の答えに、正解はない』のである。
たまに、正面からこちらの子のダメ出しをしてくる方もいらっしゃる。
そういう人は、すごく愛情を持っていただいているか、まったく人の心が読めないかのどちらかである。(主に後者だろうが…)
ついでですが、自分の子ががんばったとき、親として、しっかり褒めてあげましょう。
ただし、他人の目に触れないところでね。
野球小僧
時々、耳にしませんか?野球小僧って言葉。
「あいつ、野球小僧だからね」
・・・?
野球している子どもはみんな野球小僧?
いいえ、違います。
野球が上手=野球小僧?
いいえ、違います。
野球小僧は、野球小僧なのです。
野球小僧は、野球が上手です。
でも、野球が上手な子が全て野球小僧ではありません。
野球小僧は、ものすごく野球が好きです。
なんとなく聞かなくてもわかります。
ほっといても、野球をします。
ほっといても、野球が上手になるため練習します。
当然のように、プロ野球中継を見ます。
プロ野球選手に詳しいです。そもそも野球に詳しいです。
生活と野球が結びついています。当たり前のように。
野球以外のスポーツもできます。
でも、好んではしません。
野球しかしません。
監督、コーチのなかには、この野球小僧であることを重視する方もいます。
うちの子3人は、野球が好きだったと思います。
三男は中学生で、硬式クラブチームに入り、エース候補にもなりました。
親バカですが、投げるのも打つのも非凡なものがあったと思います。
でも、野球小僧ではありませんでした。
(それは何となくわかりました)
あいまいな説明で申し訳ない。
でも、長年、少年野球に携わると、相手チームの子でも、なんとなくわかるのです。
「ああ、あいつ、野球小僧だな」と。

バレル理論で打つ子ども
大谷翔平をはじめ、日本人が海を渡って移籍することが増え、メジャーリーグの試合が身近なものになった。
そんな中、聞いたことがあるだろうか。
『フライボール革命』
『バレルゾーン』
という言葉。
詳しくは述べないが(そもそも詳しくないが)、打球速度に応じたヒットや長打になりやすい打球の角度をいう。
いい加減な言い方で申し訳ないが、昔から教えられてきた『上から叩け』は古いという理論。
だが、私は見た。
上から叩けの時代に、『バレル理論』で打つ子どもを!(ぎゃー)
練習試合の相手チーム、その子は3番を打っていた。
左打席に入る。
まず、構えが違う。
ガッチリ脇を締め、バットを頭の後ろに垂直に立てる。
背筋もピンと立てる。腰は割らない。
その姿に、我がチームの野球経験者のお父さんさん達が(ん?)という感じで見入る。
自慢になるが、その時ピッチャーだったうちの三男は、球は速い。特に高めを長打されたことはほとんどない。
たが、打席の彼は、悠然と低めを見送る。
まるで(自慢の高めを投げてこいよ)と言っているかのように。
そして投げた高めの速球。
脇を締めたままトップをつくり、ギリギリまで呼び込んだ投球を、まるで真上に向かって打つようなスイングではね上げる。
打球はライトへ高々と上がる。
一瞬ライトフライかなっ思ったが、打球はファールゾーンのかなり遠くに停めている車の屋根に当たって跳ねて行った。
何という飛距離!
グラウンド全体がざわめく。
「あれって」
野球経験者のお父さんが言う。
「何だっけ?バレル理論?」
「そうそう」
別のお父さんが反応。
「いやー、子どもであれをやる?」
「すごいですね」
我がチームのお父さんたちが盛り上がる。
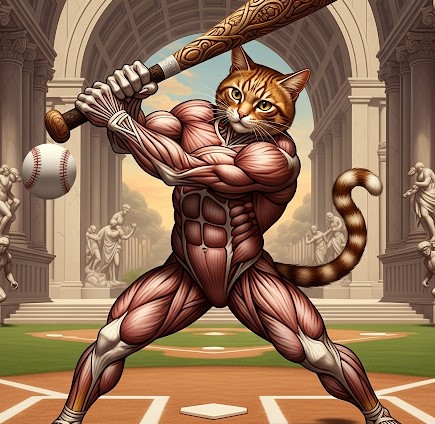
どうやら、フライボール革命なんて言葉が聞かれない時代から、バレル理論というものは、野球界にはあったようだ。
単純に高い打球を打てば、打球は飛ぶという考え方らしい。実践する日本人は少なかったようだが。
しかし、そんな打ち方、そのチームの指導者がよく認めてるなぁと、その時は感心した。
親がよほど熱心だったのだろう。
でも、なんだか野球の奥深さを知ったような感じで、今も記憶に残っている。
きっとその子の父親は、10年後、ヤンキースのジャッジを見て「ほら、見てみろ!」と叫んだだろう。
異端とは、ときに時代の先駆けである。